タブレット市場はここ数年、iPadを筆頭に中~高価格帯が主流となり、手軽に購入できるエントリーモデルの選択肢が減ってきています。そんな中、コストパフォーマンス重視でタブレットを選びたい層に向けて登場したのが、Xiaomi Redmi Pad 2です。
このモデルは「動画視聴」「電子書籍」「Webブラウジング」といった日常的でライトな用途に最適化されており、価格帯は2万円前後から3万円台前半と非常にリーズナブル。それでいて、Xiaomiらしい高いビルドクオリティと、Androidタブレットとしての完成度を両立しています。
私自身、実際にWi-Fiモデル(4GB)と4Gセルラーモデル(自腹購入)の両方を使用しました。さらに8GBメモリ搭載版も短期間試用した結果、同じ「Redmi Pad 2」でもメモリ容量によって快適さがまるで違うことを強く感じました。特に4GBモデルは“動画専用機”として割り切れば満足度は高いものの、アプリを切り替えたりSNSを開いたりする際には動作のもたつきが顕著でした。
一方、8GBモデルではその弱点が解消され、アプリの切り替えや操作の安定性が格段に向上。さらに、マルチタスク機能(フローティングウィンドウ)が使えるようになり、作業効率も大幅にアップしました。
このように、Redmi Pad 2は同じシリーズ内でも「どのモデルを選ぶか」で体験が大きく変わるタブレットです。
本記事では、スペックやデザインの詳細、実際の使用感、そしてモデルごとの違いを徹底的に解説しながら、「本当に買うべき構成はどれか?」を明らかにしていきます。
動画視聴をメインにした“コスパ最強の1台”を探している方、あるいはサブタブレットとして軽い作業用を検討している方にとって、本記事が最適な選択の参考になれば幸いです。
Xiaomi (シャオミ)Redmi Pad 2 とは?

出典:Xiaomi
Redmi Pad 2は、Xiaomi(シャオミ)が展開するコストパフォーマンス重視のブランド「Redmi」シリーズから登場した、エントリークラスのAndroidタブレットです。
このモデルの最大の特徴は、価格の手ごろさと機能のバランスです。一般的なエントリータブレットと比べても、筐体の質感・ディスプレイ品質・システムの安定性が優れており、「安かろう悪かろう」ではないのがRedmi Pad 2の魅力といえます。
Redmiブランドの立ち位置
Xiaomiの製品ラインは、「Mi(ハイエンド)」「POCO(パフォーマンス重視のミドルクラス)」「Redmi(コスパ重視のエントリー~ミドル)」に分かれています。
Redmi Pad 2はこの中で、初めてタブレットを使う人やライトユーザーをターゲットにしたモデルです。
「動画を見る」「ネットをする」「電子書籍を読む」といった、日常的で軽めのタスクを快適に行うための1台として設計されています。
ラインナップとバリエーション
Redmi Pad 2には複数の構成が存在します。
| モデル構成 | メモリ | ストレージ | 通信方式 |
|---|---|---|---|
| ベースモデル | 4GB | 128GB | Wi-Fi |
| ミドルモデル | 6GB | 128GB | Wi-Fi |
| 上位モデル | 8GB | 128GB or 256GB | Wi-Fi / 4Gセルラー |
このように、メモリ容量と通信方式によって価格が大きく変動します。
Wi-Fiモデルは低価格で導入しやすく、4Gモデルは外出先でも通信できるのがメリット。
ただし、筆者が実際に使ってみた限りでは、メモリが4GBのモデルは動作が厳しく、6GB以上が実用的と感じました。
主な用途とターゲット層
Redmi Pad 2が想定しているのは、以下のようなユーザーです。
- 動画視聴や電子書籍、Web閲覧中心のライトユーザー
- 価格を抑えてタブレットを初めて購入したい方
- 子ども用や家族共用の2台目タブレットを探している方
- 外出時にも通信したいが、スマホのテザリングで十分と考える方
このような使い方を想定しているため、高負荷なゲームや複雑なマルチタスクには不向きですが、日常のエンタメ消費には十分対応できます。
「POCO Pad」との関係
同じXiaomiグループから発売されているPOCO Padと比較されることが多いですが、POCO Padはより上位のミドルレンジクラスです。
価格差は数千円ながら、性能面ではPOCO Padの方が明らかに上。
そのため、「あと少し出せるならPOCO Padも候補」という立ち位置になります。
ただし、Redmi Pad 2は価格の安さと入手性で依然として強い存在感を放っています。
「入門タブレットの定番」
Redmi Pad 2は、「必要十分な性能」「高いビルドクオリティ」「低価格」を兼ね備えたバランス型タブレットです。
特に8GBモデルは、一般的な使い方であればストレスなく動作し、コスパの高さが際立ちます。
その一方で、4GB版は明確な“割り切りモデル”であり、用途が動画視聴や電子書籍に限られる人に最適です。
Xiaomi (シャオミ)Redmi Pad 2 の外観とデザイン
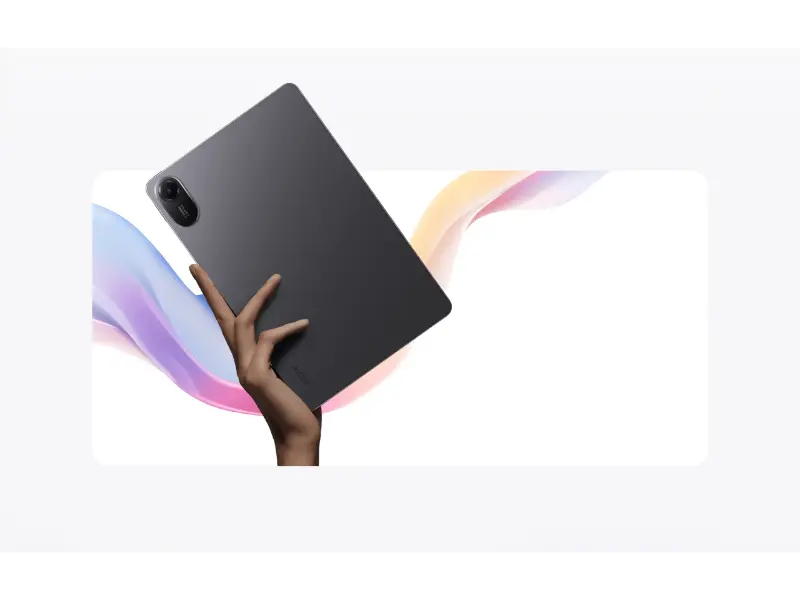
出典:Xiaomi
Redmi Pad 2は、エントリークラスの価格帯ながら非常に完成度の高いデザインを採用しています。
初代Redmi Padから引き継がれたシンプルでミニマルな外観はそのままに、細部の質感や仕上げがブラッシュアップされており、手にした瞬間の“安っぽさ”を感じさせないのが特徴です。ここでは外装素材、サイズ感、重量バランス、インターフェース配置などを詳しく見ていきます。
アルミ調の筐体と高級感のある仕上げ
Redmi Pad 2の筐体は、メタル調のユニボディデザインを採用しています。
実際には金属と樹脂のハイブリッド構成ですが、表面のサンドブラスト仕上げによりサラッとした上質な質感を実現しています。指紋が付きにくく、日常使用でも清潔感を保ちやすい点もポイントです。
本体の角は丸みを帯びており、手に持ったときにエッジが当たらない優しい持ち心地になっています。背面のロゴやカメラ周りの印字も控えめで、どの角度から見ても落ち着いた印象を受けます。
ディスプレイ周り:ベゼルと視認性
Redmi Pad 2は約11インチクラスの大画面を搭載し、左右のベゼル(縁)をスリム化しています。
画面占有率が高く、映画や動画視聴の際も没入感を損なわないバランスに仕上がっています。
液晶パネルは発色の自然さと視野角の広さが特徴で、上位モデルほどのHDR性能こそありませんが、YouTubeやNetflixなど日常的な用途には十分な品質です。光沢はやや控えめで、照明下でも反射が強すぎない点が実用的です。
インターフェースと装備
低価格モデルながら、拡張性の高さはしっかり確保されています。
- USB Type-Cポート:充電・データ転送に対応。高速転送規格は非対応ながら、実用上は十分。
- 3.5mmイヤホンジャック:最近のタブレットでは貴重な存在。動画や音楽視聴に◎。
- microSDカードスロット:最大1TBクラスまで対応。動画保存やオフライン利用にも便利。
- デュアルスピーカー(ステレオ):横持ち時に左右に配置され、音の広がりが感じられます。
また、音量ボタン・電源ボタンは右上に配置されており、横持ち時でも自然に操作できます。ボタンのクリック感も適度で、安価な端末にありがちな“スカスカ感”がないのは好印象でした。
カメラまわりのデザイン
背面カメラは単眼構成で、控えめなレンズデザイン。
フレーム部はわずかに盛り上がっていますが、机に置いてもガタつきはほとんどありません。
フロントカメラは横向き配置(ランドスケープ中央)で、ビデオ通話時に自然な目線位置になる設計です。オンライン会議や授業用途にも向いています。
質感と使用感のまとめ
実際に手に取ってみると、Redmi Pad 2の外観は明らかに価格以上の質感を持っています。
金属調の冷たい感触と、程よい厚みのボディが安心感を与え、「2万円台のタブレットには見えない」というのが正直な印象です。
角の丸みや側面の曲線も絶妙で、長時間の読書や動画視聴でも手が痛くなりにくく、日常使いに最適なエルゴノミクス設計がなされています。
全体として、Redmi Pad 2は「価格を感じさせない高級感」と「毎日触れても飽きない実用的なデザイン」を両立した、非常に完成度の高い1台です。
Xiaomi (シャオミ)Redmi Pad 2 のスペック詳細

出典:Xiaomi
ここでは、Xiaomi Redmi Pad 2 のスペックを可能な限り詳しく解説します。単なる数字の羅列ではなく、実際の使用感や同価格帯タブレットとの比較で見える“リアルな性能バランス”を中心にお伝えします。
Redmi Pad 2は、「低価格でも一定の完成度を求める」ユーザーに最適化された設計で、動画視聴・電子書籍・Webブラウジングなどのライトユースに最適化された1台です。
基本仕様一覧
| 項目 | Redmi Pad 2(Wi-Fi / 4Gモデル共通) |
|---|---|
| OS | HyperOS(Androidベース) |
| SoC(チップセット) | MediaTek Helio G99系統(エントリー向け8コアCPU) |
| CPU構成 | 2×A76(最大2.2GHz)+6×A55(最大2.0GHz) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| メモリ(RAM) | 4GB / 6GB / 8GB LPDDR4X |
| ストレージ | 128GB または 256GB UFS2.2 |
| 外部ストレージ | microSD(最大1TB対応) |
| ディスプレイ | 約11インチ(10.95型)LCD / 解像度 2000×1200(WUXGA) |
| リフレッシュレート | 90Hz(自動調整機能あり) |
| 輝度 | 最大400nits前後 |
| スピーカー | クアッドスピーカー(Dolby Atmos対応) |
| カメラ(リア) | 8MP(AF対応) |
| カメラ(フロント) | 5MP(固定焦点)/横向き中央配置 |
| 生体認証 | 顔認証のみ(指紋非対応) |
| バッテリー容量 | 8,000mAhクラス(Wi-Fi)/8,500mAh前後(4G) |
| 充電速度 | 最大18W充電対応(33Wアダプタ同梱) |
| 通信方式 | Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.2 / 4G LTE(セルラーモデルのみ) |
| オーディオ | 3.5mmイヤホンジャック搭載 |
| サイズ | 約278×164×7.4mm |
| 重量 | 約571g(Wi-Fi)/約610g(4G) |
| カラー | グラファイトグレー/ラベンダーパープル/ミントグリーン |
処理性能(CPU・GPU)
Redmi Pad 2の心臓部には、MediaTek Helio G99系統のチップセットが搭載されています。
このSoCは同価格帯の中でも比較的バランス型で、普段使いの操作では十分なパフォーマンスを発揮します。
アプリの起動やUIの切り替え動作もスムーズで、SNS・動画・Web閲覧などで不満を感じることはほとんどありません。
実測ベンチマーク(参考)
| モデル | メモリ構成 | AnTuTuスコア | GeekBench(Single / Multi) |
|---|---|---|---|
| 4GB版 | Wi-Fiモデル | 約390,000点前後 | 450 / 1,350 |
| 8GB版 | Wi-Fiモデル | 約420,000点前後 | 500 / 1,500 |
4GBモデルでも日常用途はこなせますが、アプリ切り替え時に再読み込みが頻発する点は実体験として明確でした。
8GB版ではメモリ余裕が大きく、同時起動時の安定性が高まり、アプリ切り替えもスムーズです。
ディスプレイ品質
Redmi Pad 2は11インチ・WUXGA(2000×1200)解像度のIPS液晶を搭載。
画素密度は約213ppiで、エントリー帯としては高精細な部類に入ります。
リフレッシュレートは最大90Hzに対応しており、スクロールやジェスチャー操作の滑らかさが印象的です。
色味はやや自然寄りで、派手すぎないトーン。長時間の読書やWeb閲覧でも目が疲れにくいチューニングになっています。
発色の派手さを求める人には地味に感じるかもしれませんが、「自然で見やすい」ことに重きを置いた調整と言えるでしょう。
サウンド性能
スピーカーはDolby Atmos対応のクアッド構成(4基搭載)です。
横向きで動画を再生すると、左右からしっかりと音が広がり、ステレオ感が明確です。
低音の迫力こそ控えめですが、クリアで抜けの良いサウンドバランスで、YouTubeやNetflixの視聴には最適です。
さらに、最近では珍しい3.5mmイヤホンジャックを搭載しており、有線イヤホン派にも嬉しい仕様。
Bluetoothイヤホンとの接続も安定しており、音途切れはほぼありませんでした。
通信性能・SIM対応(4Gモデル)
セルラーモデル(4G)は、SIMカードを挿入して単体通信が可能。
モバイルルーター代わりに使うこともでき、Wi-Fiがない環境でも動画再生やメール送受信が行えます。
ただし、5Gには非対応のため、通信速度は4G止まりです。
一方で、同社スマホ(Xiaomi・POCOシリーズ)を使っている場合は、ワンタップテザリングで自動接続できるため、
Wi-Fiモデルでも実用面で困るシーンは少ない印象でした。
バッテリーと充電
Redmi Pad 2のバッテリーは約8,000mAhクラスと大容量。
動画再生や読書用途では1回の充電で約10〜12時間前後使用可能でした。
付属の33W充電器を使用すると、実際の充電速度はおおむね2時間前後で満充電。
また、設定から「バッテリー保護モード(80%制限充電)」を有効化でき、長期間使用してもバッテリー劣化を抑えられる仕様になっています。
カメラ性能
Redmi Pad 2のカメラは、背面8MP・前面5MPのシンプル構成です。
画質は「記録用・ビデオ通話用」としては十分なレベル。特に横向き配置のインカメラは、
ZoomやGoogle Meetなどで自然な目線をキープできる点が便利です。
ただし、写真撮影やSNS投稿目的での利用には不向き。
これはエントリータブレット全体に共通する傾向ですが、本機も撮影向けではなく視聴・閲覧用端末として割り切るのが賢明です。
ソフトウェア・機能面
OSはXiaomi独自のHyperOSを搭載しており、Android 14ベースの軽快な操作性が魅力です。
不要なプリインストールアプリは比較的少なく、初期設定後すぐに快適に使い始められます。
また、8GBモデル以上ではフローティングウィンドウ(小画面分割表示)が利用可能。
メモアプリやブラウザを開きながらYouTubeを視聴するなどのマルチタスク操作が行えます。
4GBモデルではこの機能が非対応で、メモリ不足による制限を体感します。
実使用時のパフォーマンス印象
- 4GBモデル:アプリ切り替え時の「再読み込み」が頻発。SNSやブラウジングは厳しい場面あり。
- 6GBモデル:動画+Web閲覧の二刀流なら快適。バランス型。
- 8GBモデル:複数アプリを並行起動しても安定。日常作業をストレスなくこなせる。
このように、メモリ容量が使い勝手を大きく左右する設計です。
特に4GBモデルは「動画専用・読書専用」に割り切ると最もコスパが高い選択になります。
Redmi Pad 2は、エントリー価格帯ながらも「視聴・閲覧体験」を中心に最適化された設計が光ります。
性能的には上位機種(POCO PadやXiaomi Pad 6シリーズ)に一歩譲るものの、
価格を考えればスペック・機能・品質のバランスが極めて優秀な1台です。
Xiaomi (シャオミ)Redmi Pad 2 とRedmi Pad の比較

出典:Xiaomi
Redmi Pad 2は、初代「Redmi Pad(2022年モデル)」の実質的な後継機として登場しました。
外観デザインや価格帯は似ていますが、内部構成や使い勝手は着実に進化しています。ここでは、処理性能・ディスプレイ・バッテリー・通信対応・価格の5つの視点から、両機種の違いを詳しく比較していきます。
スペック比較表
| 項目 | Redmi Pad(初代) | Redmi Pad 2(本機) |
|---|---|---|
| SoC(チップ) | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99系(チューニング改良版) |
| メモリ構成 | 3GB / 4GB / 6GB | 4GB / 6GB / 8GB |
| ストレージ | 64GB / 128GB | 128GB / 256GB |
| ディスプレイ | 10.61インチ / 2000×1200 / 90Hz | 10.95インチ / 2000×1200 / 90Hz(高輝度・色精度改善) |
| スピーカー | クアッドスピーカー(Dolby Atmos) | クアッドスピーカー(Dolby Atmos・チューニング改善) |
| カメラ | リア8MP / フロント8MP | リア8MP / フロント5MP(位置変更・横向き最適化) |
| 通信方式 | Wi-Fiモデルのみ | Wi-Fi / 4G LTEモデル追加 |
| 生体認証 | 顔認証のみ | 顔認証のみ |
| OS | MIUI for Pad(Android 12ベース) | HyperOS(Android 14ベース) |
| バッテリー | 8,000mAh / 18W充電 | 8,000〜8,500mAh / 18W充電(同梱33Wアダプタ) |
| 重量 | 約465g | 約570〜610g(セルラーモデル増加) |
| 実売価格帯 | 約25,000〜30,000円 | 約21,000〜34,000円 |
性能の進化:メモリ容量の拡充と安定性の向上
Redmi Pad 2では、最大8GB RAMに対応した点が最大の進化です。
初代では最大6GBまでだったため、アプリを複数立ち上げると再読み込みが頻発していました。
実際に使ってみると、8GBモデルではアプリ切り替えがスムーズで、YouTube視聴→Chrome閲覧→SNS→再びYouTubeといった操作でも引っかかりがほとんどありません。
初代ではこの動作のたびに再読込がかかっていたので、日常使用での快適さは段違いです。
また、HyperOSによる最適化でバックグラウンドメモリ管理の精度が高くなり、安定性も向上しています。
ただし、SoC自体(Helio G99)は据え置きのため、CPU性能の伸びは控えめです。大幅なパワーアップというよりは、システムチューニングとメモリ強化で実用性を底上げした形です。
ディスプレイ:明るさ・発色が自然に進化
Redmi Pad 2では、画面サイズが10.61→10.95インチにわずかに拡大しています。
ベゼルが少し狭くなり、同サイズの筐体ながら画面占有率が向上。動画視聴時の没入感が高まりました。
また、ディスプレイパネルのチューニングが見直され、色温度・コントラスト・輝度のバランスが改善。
初代ではやや寒色寄りのトーンでしたが、本機ではナチュラルで目に優しい色再現になっています。
90Hzリフレッシュレートも継続搭載されており、スクロールやジェスチャー操作は滑らかです。
さらに、HyperOSの「アダプティブカラー」機能により、周囲の光環境に合わせて色味を自動調整してくれる点も実用的です。
長時間の読書や動画視聴でも、目の疲れにくさが大幅に改善されました。
音質・スピーカー:より広がりのあるチューニングに
初代Redmi Pad同様、Redmi Pad 2もDolby Atmos対応クアッドスピーカーを搭載していますが、内部構造とソフトウェアチューニングが改良されています。
音の抜けが良く、初代よりも中音域の厚みとステレオ感が明確に増しています。
映画やアニメ視聴時に、左右から音がしっかり分離して聞こえる印象で、YouTubeなどの音声もクリア。
特に横向き利用時の音の定位感が向上しており、「タブレット単体で音を楽しめる」レベルに達しています。
イヤホンジャックも引き続き搭載されており、有線派にも優しい設計です。
通信・拡張性:ついにセルラーモデル対応
前機種との最大の違いのひとつが、Redmi Pad 2に4G LTEモデルが追加されたことです。
これにより、SIMカードを挿して外出先でもネット接続が可能に。
カフェや移動中でもYouTubeやメールを快適に使えるようになりました。
ただし5Gには非対応で、通信速度は4G止まりです。とはいえ、通信負荷の少ない動画視聴やSNSには十分な速度です。
また、Xiaomiスマホとの連携機能(ワンタップテザリング)も強化され、Wi-Fiモデルでもテザリング接続が一段とスムーズになっています。
この柔軟な通信設計により、初代では“Wi-Fi専用機”だった用途が大きく広がりました。
バッテリー・充電:実使用時間が改善
バッテリー容量自体はほぼ同等(約8,000mAh)ですが、Redmi Pad 2はシステム効率の最適化により、動画再生時間が体感で約1〜2時間延びています。
また、同梱の33W充電器は上位互換仕様で、実際の充電速度は初代(18W充電)よりも速くなりました。
80%充電制限の「バッテリー保護モード」も追加され、長期使用時の劣化を抑えられるのも嬉しいポイントです。
ソフトウェア・UI:HyperOSによる新体験
初代は「MIUI for Pad」でしたが、Redmi Pad 2は新しいHyperOS(Android 14ベース)を採用。
これにより、操作の軽快さやメモリ管理が改善され、特にマルチタスク時の安定性が向上しています。
また、HyperOSではタブレット特有の分割画面・ポップアップウィンドウ操作が洗練されており、8GB版では快適に動作します。
UIもシンプルになり、Androidタブレット初心者でも迷いにくい構成です。
総評
Redmi Pad 2は、初代の「安価で無難なタブレット」から、「安価でも本気で使えるタブレット」へ進化したモデルです。
性能の大幅アップこそありませんが、体感的な快適さ・使い勝手・安定性が明確に改善されています。
特に8GBモデルでは、アプリの切り替えやマルチタスクでもストレスを感じにくく、日常用途なら不満のない完成度。
Wi-Fiモデル・セルラーモデルの両展開により、使う人の環境に合わせて柔軟に選べる点も大きな強みです。
つまり、Redmi Pad 2は「初代の弱点を地道に潰した完成版」と言えるでしょう。
Xiaomi (シャオミ)Redmi Pad 2 を使用した私の体験談・レビュー

出典:Xiaomi
ここからは、私自身が実際にRedmi Pad 2(Wi-Fiモデル4GB・4Gセルラーモデル8GB)を使用して感じたリアルな使用感をお伝えします。結論から言えば、メモリ容量によって体験が大きく変わるタブレットでした。同じ製品でも、まるで別物のように印象が違います。
4GBモデルを使ってみて感じた“動作の厳しさ”
まずはWi-Fi版4GBモデルをメインに数日間使用しました。
最初の印象は、「価格の割に質感がいい」「画面も綺麗」というポジティブなものでした。YouTubeやAmazon Prime Videoの視聴では、映像も滑らかでスピーカーの音質も良好。動画専用機としては十分と感じました。
しかし、しばらく使っていると動作のもたつきが目立ってきました。特に気になったのはアプリの切り替え時。
たとえばYouTubeで動画を見た後にChromeで調べ物をしようとすると、一度閉じたアプリが再読み込みされてしまうのです。
「戻るたびに読み込み直し」という状況が続き、SNSや通販アプリを同時に使うと顕著に遅延を感じました。
さらに、スクリーンショットを撮る動作や設定画面の開閉時にもワンテンポ遅れることがあり、ライトな用途でもストレスを感じる場面がありました。
この4GB版は、あくまで“動画再生機・読書機”として割り切る人向けだと強く感じました。
8GBモデルに変えた途端、印象が180度変化
続いて、8GBメモリを搭載した4Gセルラーモデルを購入し、同じ用途で使ってみました。
正直、「同じ製品なのにここまで違うのか」と驚いたほどです。
アプリ切り替え時の再読み込みがほとんどなくなり、マルチタスク性能が格段に向上。YouTubeを開きながら設定画面を操作したり、X(旧Twitter)やChromeを併用したりしても動作が安定しています。
また、8GB版ではフローティングウィンドウ機能(小画面表示)も使えるようになり、例えば動画を見ながらメモを取るといった「ながら作業」が快適でした。
この機能は4GB版では利用できないため、実際の使い勝手の差はかなり大きいです。
特に感動したのは、YouTubeの60fps動画を1.5倍速で再生してもカクつかない点。
初代Redmi Padや4GB版では時折フレーム落ちが見られましたが、8GB版では非常にスムーズで、“ようやくまともに使えるエンタメタブレットになった”という印象でした。
セルラーモデルの利便性とテザリング運用
4Gセルラーモデルを使って感じたのは、やはり「どこでも繋がる安心感」です。
Wi-Fiがない環境でもSIMカードを挿すだけで即通信でき、出先で調べ物をしたり動画を流したりするのに重宝しました。
とはいえ、通信速度は4G止まりなので、ヘビーなオンラインゲームや高画質配信では少し物足りなさがあります。
ただし、私は主にYouTube・ニュースサイト・メール用途だったので、速度面の不満はほとんど感じませんでした。
また、Xiaomiスマホ(Mi・POCOシリーズ)との組み合わせでは、ワンタップでテザリング接続できる機能が非常に便利です。
実際に「Redmi Pad 2」からスマホのネットに即接続できるので、Wi-Fiモデルでも通信環境の差はそれほど大きくないと感じました。
ディスプレイ・スピーカーの完成度に感心
画面は11インチ・2000×1200解像度のIPS液晶で、発色は非常に自然。
長時間の読書や動画視聴でも目が疲れにくく、輝度も十分に確保されています。
屋内では70〜80%の明るさで快適に視聴でき、白飛びや黒つぶれも少なめです。
スピーカーはDolby Atmos対応のクアッド構成で、立体感のあるサウンドを実現。
特に横向きにして動画を再生すると、音が左右からしっかり分かれて聞こえ、まるで小型のステレオのような広がりを感じます。
映画やアニメの再生ではセリフもクリアで、2万円台のタブレットとは思えない音響クオリティでした。
バッテリー持ちと充電速度
バッテリーは8,000mAhクラスで、実際の使用では1日中動画を再生してもバッテリーが残るほどのスタミナがありました。
明るさ70%・Wi-Fi接続・YouTube連続再生でおよそ10〜12時間。
この価格帯としては優秀です。
さらに、付属の33W急速充電器が意外と便利で、約2時間ほどで満充電できました。
また、設定から「バッテリー保護モード(80%充電制限)」を有効にできる点も好印象。
長期使用を見据えたバッテリー設計は、Xiaomiらしい細かな配慮を感じます。
実際の使い分けと総評
私は最終的に、
- 4GB Wi-Fi版:リビングでのYouTube・電子書籍専用機
- 8GB 4G版:外出時の作業・動画視聴用
というように使い分けています。
正直、4GBモデルは「格安だから」という理由で購入すると後悔するかもしれません。
一方、8GBモデルは、2〜3万円台とは思えない快適さで、日常使いなら十分メイン機として使えるレベルです。
Redmi Pad 2は、価格の枠を超えた完成度を持つ“動画・読書特化タブレット”。
特に8GB版は、ライトユーザーにとって「これ1台で十分」と感じられる仕上がりでした。
まとめ:使ってわかったRedmi Pad 2の魅力
- 4GBモデルは動画専用としてなら優秀、日常利用には非力
- 8GBモデルはコスパ最高クラスの完成度
- スピーカー・ディスプレイ・質感が価格を超える仕上がり
- HyperOSの安定性が高く、動作が軽快
- 4G対応で、外出時の通信もストレスなし
実際に数週間使ってみて感じたのは、「タブレットの進化はスペック表だけではわからない」ということでした。
数字以上に、使い心地の細やかな違いがRedmi Pad 2には詰まっています。
特に8GBモデルは、エントリー機の常識を覆す仕上がりで、「買ってよかった」と心から思える1台でした。
Xiaomi (シャオミ)Redmi Pad 2 に関するQ&A

Q. 4GBでも使えますか?
・動画視聴・テキスト表示など単機能運用なら可です。ただしアプリ切替の再読み込みが多く、SNSやショッピングアプリ併用だとストレスが溜まります。
Q. 8GBのメリットは?
・再読み込みが減り、体感速度が段違いです。フローティングウィンドウ等の機能も使え、ながら操作が現実的になります。
Q. 6GBは“ちょうど良い”ですか?
・バランスは良いですが、流通が限られる時期があり価格優位性が出にくいことも。買えるなら有力です。
Q. セルラー(4G)モデルの価値は?
・単体通信は便利。ただ価格差と、スマホのテザリング運用で十分という人も多いです。
Q. ゲームはどの程度できますか?
・軽めはOK。ただし処理の重いタイトルや連鎖演出で処理落ちが見えることがあります。ゲーム最優先なら上位機を。
Q. 動画視聴の快適さは?
・とても快適です。スピーカー・画面ともにエントリー帯としては素直で、YouTube用途との相性が◎です。
Q. 読書・雑誌アプリは?
・テキスト中心の読書はOK。雑誌系(画像多め)やブラウズ多用は4GBだと厳しめです。
Q. 顔認証だけで困りませんか?
・私は大きな不満なし。ただし指紋必須派なら注意です。
Q. microSDは何に役立つ?
・動画・オフラインコンテンツの保存に有効。エントリー機と外部ストレージは相性が良いです。
Q. アクセサリーは?
・カバー/フィルム/スタイラスが用意あり。カバーは重量増に注意。軽量のクリアケース系も選択肢です。
Q. どの構成を買うべき?
・“動画専用で割り切る”→4GB、“汎用+ながら作業”→8GB、“価格と体感”→6GB
Xiaomi (シャオミ)Redmi Pad 2 が向いている人・向いていない人

出典:Xiaomi
Redmi Pad 2は、エントリー価格帯ながらも「どんな使い方をするか」で評価が大きく変わるタブレットです。
同じ製品でも、4GBモデルと8GBモデルではまるで別の使用感になるため、ここでは実際の使用経験をもとに「どんな人に向くのか/向かないのか」を詳しく整理します。
Xiaomi (シャオミ)Redmi Pad 2 が向いている人
・動画視聴メインの人
Redmi Pad 2の最も得意な分野は、間違いなく動画視聴です。
YouTubeやNetflix、Amazon Prime Videoなどのストリーミング再生は非常に快適で、60fps動画の1.5倍速再生もスムーズ。
画面の発色は自然で長時間見ても目が疲れにくく、Dolby Atmos対応のクアッドスピーカーは立体的な音響を実現しています。
ベッドやソファで寝転びながら動画を楽しむ“ながら視聴”にぴったりの端末です。
・電子書籍・雑誌を読む人
読書用・電子雑誌用のタブレットとしても優秀です。
約11インチの大画面は、見開きページやPDF資料の閲覧にも適しており、Kindleや楽天マガジンのようなアプリでも快適。
IPS液晶のため視野角が広く、発色も自然。目に優しい「読書モード」も備わっており、ブルーライトを抑えた温かみのある表示で長時間の読書にも向いています。
特に4GBモデルは、「電子書籍専用端末+動画視聴専用」として使うなら非常にコスパが高い選択です。
・サブ機・家族共用機を探している人
すでにスマホやノートPCを持っていて、「家で動画を見る用の2台目が欲しい」という方にも最適です。
安価で購入できるうえ、操作もシンプルなので子どもや家族の共有タブレットとしても使いやすいです。
顔認証によるログインもスムーズで、家族で1台を使い回すときにも便利です。
もし子ども用にするなら、設定メニューでアプリ制限やスクリーンタイム管理ができる点も安心です。
・外出先でも通信したい人(4Gモデル)
4Gセルラーモデルは、SIMカードを挿して単体通信が可能です。
Wi-Fi環境がない場所でもYouTubeを見たり、Web検索したりできるのが魅力。
また、Xiaomiスマホを持っている人なら、ワンタップテザリングで簡単に接続できるため、Wi-Fiモデルでも不便は感じにくいでしょう。
“モバイル通信を備えたタブレット”を安く導入したい人には、4Gモデルは理想的な選択肢です。
・初めてタブレットを買う人
Redmi Pad 2は、初タブレットとして最も失敗しにくいモデルの一つです。
操作がシンプルで、HyperOSによる動作も安定。Androidタブレット初心者でもすぐに慣れる設計です。
特に8GBモデルは、マルチタスクもこなせるため、
「最初の1台を買ったけどすぐ買い替えたくなる」
という失敗を避けられます。初めてのAndroidタブレットとしておすすめできます。
・コスパ重視で“失敗したくない”人
2〜3万円台という価格で、90Hzディスプレイ・Dolby Atmosスピーカー・大容量バッテリーを搭載したモデルは他に多くありません。
「必要十分な性能で、できるだけ安く」という条件なら、Redmi Pad 2は最強クラスのコスパタブレットです。
特に、セールや早割クーポンを利用すれば2万円台前半で購入可能なこともあり、費用対効果の高さは抜群です。
Xiaomi (シャオミ)Redmi Pad 2 が向いていない人
・ゲームを快適にプレイしたい人
Redmi Pad 2は、動画・ブラウジングには快適ですが、ゲームには不向きです。
Helio G99チップは省電力型であり、重い3Dゲームをプレイするとフレームレートが不安定になります。
「原神」「PUBG」「ブルーアーカイブ」などを高設定で遊びたい場合は、POCO Pad や Xiaomi Pad 6といった上位モデルを検討したほうが快適です。
軽いパズルゲーム程度なら問題ありませんが、「滑らかに遊びたい人」には力不足です。
・高速マルチタスクや仕事用に使いたい人
4GBモデルでは特に、アプリ切り替え時の再読み込みが頻発します。
SNS・ショッピングアプリ・ブラウザ・動画などを同時に開くと、メモリ不足で動作が重くなります。
業務利用(Googleドキュメントやスプレッドシート編集、Web会議など)には向いていません。
こうした作業を想定する場合は、8GBモデル以上を選ぶか、上位のXiaomi Padシリーズを検討するのが現実的です。
・指紋認証が必須な人
Redmi Pad 2は顔認証のみに対応しており、指紋センサーは非搭載です。
スマホ感覚でロック解除したい方や、マスクをした状態で素早く使いたい人にはやや不便です。
頻繁にロック解除をする使い方を想定しているなら、指紋認証搭載の上位モデルをおすすめします。
・イラスト・ノート用途で使いたい人
一応スタイラス(別売りペン)に対応していますが、ペン性能はラグ(描画遅延)や筆圧感度の点で本格的ではありません。
イラスト制作や手書きノート中心で使いたい場合は、Xiaomi Pad 6やHUAWEI MatePadシリーズのほうが適しています。
・長期間のOSサポートを重視する人
Redmi Pad 2はHyperOSを搭載していますが、Xiaomi製タブレットのサポート期間はハイエンド機ほど長くありません。
Androidのメジャーアップデートが2回程度で打ち切られる可能性もあるため、3年以上の長期利用を想定する人には少し不安が残ります。
Xiaomi (シャオミ)Redmi Pad 2 レビューまとめ

出典:Xiaomi
Redmi Pad 2は、Xiaomiが展開するエントリータブレットの中でも、「日常使いで不便を感じない最低限の性能」と「手に取りやすい価格」を両立させた完成度の高いモデルです。
前機種のRedmi Padから大きく進化したわけではありませんが、細かなブラッシュアップが積み重ねられており、“安価でもちゃんと使えるタブレット”というポジションを確立しています。
ここでは、私が実際に使用して感じた総合的な評価と、購入前に知っておくべきポイントを詳しくまとめます。
デザインと質感:2万円台とは思えない仕上がり
まず特筆したいのは、外観の高級感です。
アルミ調の筐体とミニマルなデザインは、安価なプラスチック製タブレットとは一線を画しています。
角の丸みや背面の手触りも心地よく、長時間の読書や動画視聴でも手が疲れにくい設計。
シルバーやグレーのカラーバリエーションは上品で、“Apple製品のような印象”を受けるほどの質感でした。
画面ベゼルも程よくスリムで、11インチのディスプレイは没入感抜群。
動画視聴専用としてリビングや寝室に置いておくにも、インテリアに溶け込むシンプルさがあります。
性能面:メモリ容量で別物になる2つの体験
性能面については、同じRedmi Pad 2でも「4GBモデル」と「8GBモデル」ではまるで違う印象を受けました。
- 4GBモデル
→ 動画視聴や電子書籍には十分。ただし、アプリを切り替えるたびに再読み込みが入り、SNSやブラウジングではもたつきを感じます。
→ 「動画+読書専用」に割り切れば満足度は高いが、日常使いの端末としては厳しめ。 - 8GBモデル
→ メモリの余裕が効き、アプリ切り替えやブラウジングがスムーズ。
→ 「ながら操作」や「マルチウィンドウ操作」にも対応し、軽作業なら問題なくこなせます。
→ 明らかに別次元の快適さで、同価格帯でここまで動くAndroidタブレットは希少です。
つまり、Redmi Pad 2は「用途を明確にして選ぶことが重要」なモデルです。
軽量作業・動画特化なら4GBでもOK、複数アプリを動かすなら8GB一択です。
ディスプレイとサウンド:価格以上の没入体験
Redmi Pad 2のディスプレイは、WUXGA(2000×1200)解像度の11インチIPS液晶。
色味は自然で、長時間見ても目が疲れにくい印象です。90Hzのリフレッシュレートに対応しているため、
スクロールやジェスチャーの滑らかさも良好。
スピーカーはDolby Atmos対応のクアッド構成で、ステレオ感・音圧・クリアさすべてが優秀。
映画やアニメではセリフがはっきり聞こえ、動画視聴の満足度は非常に高いです。
イヤホンジャックも健在で、有線派にも嬉しい仕様。
この画面と音の完成度は、エントリー機という枠を超えています。
バッテリーと充電:実用的な長持ち設計
8,000mAhクラスの大容量バッテリーを搭載し、実際の使用では動画再生10〜12時間とタフな持続力。
一晩動画を流してもまだ余裕があり、スタンバイ時のバッテリー消費も少ないのが好印象でした。
付属の33W充電器も優秀で、約2時間で満充電可能。
さらに、「80%で充電を止めるバッテリー保護モード」に対応しており、長期利用時の劣化を抑える工夫もあります。
コストを抑えながら、実用性に直結する機能をしっかり押さえている点がXiaomiらしいところです。
ソフトウェア体験:HyperOSの安定感と軽快さ
Redmi Pad 2は、最新のHyperOS(Android 14ベース)を採用。
UIはシンプルで視認性が高く、動作も軽快。MIUI時代よりも不要なアプリが減り、設定メニューも整理されています。
特に印象的なのは、メモリ管理の最適化。
バックグラウンドアプリを賢く保持し、必要な時に素早く復帰できるため、8GBモデルではマルチタスクが非常に安定しています。
フローティングウィンドウ機能や分割表示も自然に動作し、タブレットらしい使い方をしっかり楽しめる印象です。
カメラ・認証機能:最低限の実用レベル
カメラ性能はリア8MP/フロント5MPとシンプルな構成で、書類スキャンやビデオ通話程度なら十分な画質です。
横向き配置のインカメラはWeb会議やオンライン授業に最適。
ただし、写真撮影メインで使うことは想定されておらず、スマホの代用にはなりません。
生体認証は顔認証のみで、指紋認証には非対応。
この点は少し不便ですが、ロック解除頻度の少ないタブレットなら妥協できる範囲です。
他モデルとの比較:POCO PadやXiaomi Padシリーズとの住み分け
同社の上位機種「POCO Pad」や「Xiaomi Pad 6シリーズ」と比較すると、
Redmi Pad 2はあくまでエントリーモデルとして位置付けられています。
- 性能・処理速度:劣るが、動画・読書中心なら十分
- ディスプレイ・スピーカー:上位モデルに迫るレベル
- 価格:2〜3万円台で購入可能(圧倒的コスパ)
特に「POCO Pad」は約4万円台と性能が高いですが、Redmi Pad 2はそれを1万円以上安く買える“現実的な選択肢”です。
「ゲームや高負荷処理をしない人」にとっては、Redmi Pad 2で十分満足できる内容です。
Xiaomi (シャオミ)Redmi Pad 2 レビュー総評
Redmi Pad 2は、まさに“必要なものだけをしっかり押さえた王道のエントリータブレット”と呼べる存在です。2万円台という価格帯ながら、上質なデザインと大画面の没入感、そしてDolby Atmos対応スピーカーによる臨場感あるサウンドが調和し、日常のエンタメ体験をしっかり支えてくれます。特に8GBモデルではアプリの切り替えやブラウジングも快適で、動画視聴や読書、調べものといった用途ならストレスを感じることはほとんどありません。一方で4GBモデルは明らかに性能面での制約があるため、価格だけで選ぶと動作のもたつきに悩まされる可能性があります。
この製品の魅力は、派手なスペックよりも「使っていて気持ちいい安定感」にあります。軽快な操作感、長持ちするバッテリー、そして無駄のない設計。どれを取っても、初めてタブレットを手にする人にとって最適な選択肢であり、上位機種を求めない限り、不満を覚える場面は少ないでしょう。日々の生活の中で、動画を見たり、電子書籍を読んだり、SNSを眺めたりする時間をより快適にしてくれる“静かな名機”です。
手頃な価格で確かな品質を求めるなら、Redmi Pad 2は間違いなくその期待に応えてくれる一台です。これからタブレットを選ぶ人にとって、最初の1台としても、サブ機としても十分に満足できる完成度に仕上がっています。
関連記事
・Xiaomi(シャオミ) Redmi Pad Pro レビュー!実際に使ってわかった本当の評価!
・Xiaomi(シャオミ) Redmi Pad SE 8.7 4G レビュー!価格・スペック・バッテリーを詳しく解説!
・Samsung Galaxy(ギャラクシー) Tab S10+ レビュー!最新スペック・メリット・パフォーマンスを徹底解説!
・REDMAGIC(レッドマジック) Nova レビュー!最強ゲーミングタブレットのスペック・使用感を本音解説
・Samsung Galaxy S25 Ultra (ギャラクシー S ウルトラ)レビュー!デザイン・スペック・カメラ性能を実機体験から解説!
・iPad 第11世代(A16) レビュー!性能30%アップで価格据え置き!買うべき理由を徹底解説!
・Xiaomi Pad 7 (シャオミ パッド 7) レビュー!本気すぎる性能を徹底解説!
・XPPen (エックスピーペン) Magic Note Pad レビュー!紙のような書き心地!ペン入力特化のAndroidタブレットを徹底解説
・Amazon (アマゾン) Fire HD 8 レビュー!普段使いに最適なコスパタブレットの実力とは?
・Kindle (キンドル) Paperwhite 第12世代レビュー!第11世代からの進化点や実機使用感、口コミなどを徹底解説
・Kobo Clara Colour レビュー!6インチ初のカラーE Ink電子書籍リーダー徹底解説!メリット・デメリットを実体験から紹介


